1
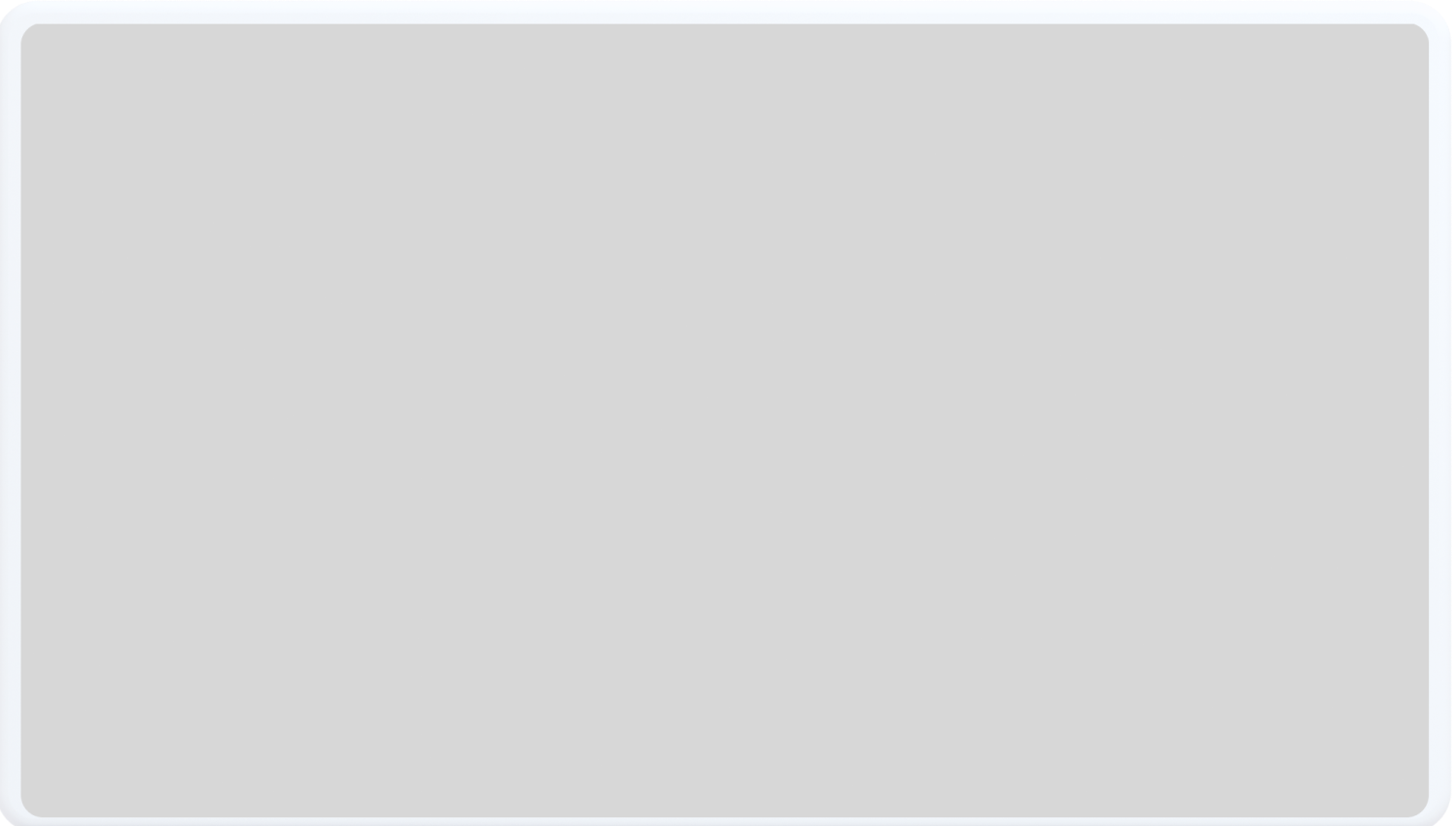
関係者間でのナレッジの共有
同一自治体内の業務マニュアル/ガイドライン/規定に書かれている知識や各担当者の経験の共有を促進します。スキルと経験の属人化を防ぎ、人々の生活を左右する重大な判断を下す責任のある仕事をサポートすることが可能です。単語によるキーワード検索で、過去のノウハウを即時表示します。同意が得られれば、自治体間でのナレッジ共有も行うことが可能です。
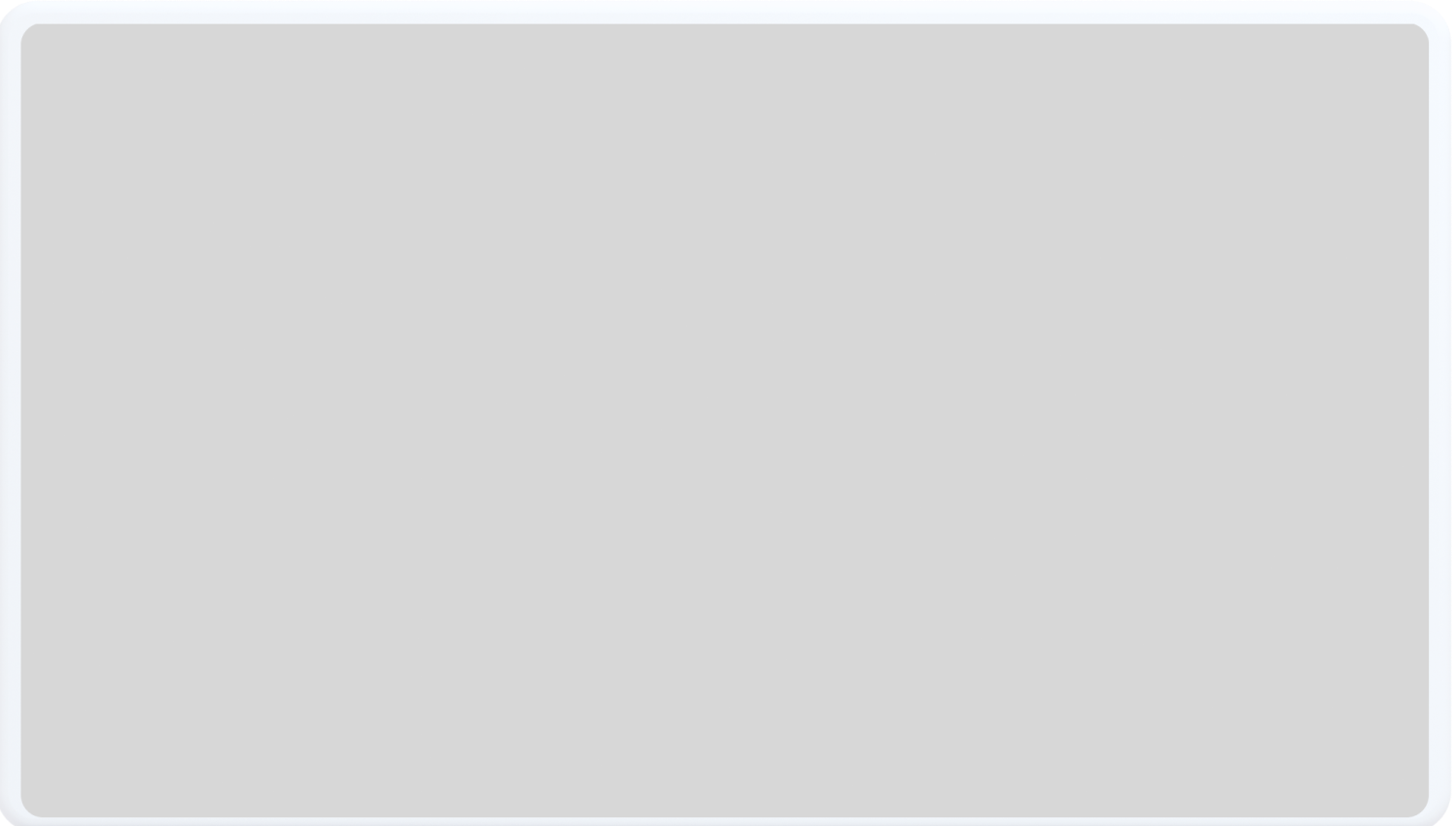

児童相談所における課題
相談ケースの件数増加や慢性的な人材・体制の不足、ペーパーワークの負荷増大、社会的養護体制の不足等児童相談所を取り巻く環境は非常に過酷な状況となっています。
本日は、現場が抱える多様な課題をデジタル技術を活用してどの様に変革できるかをご紹介いたします。
こちらがシステムに最初にログインした際に表示されるトップページです。児童福祉司・児童心理司が抱えている案件の状況をダッシュボードや一覧において確認することができます。また、本日の予定や承認状況も確認できます。
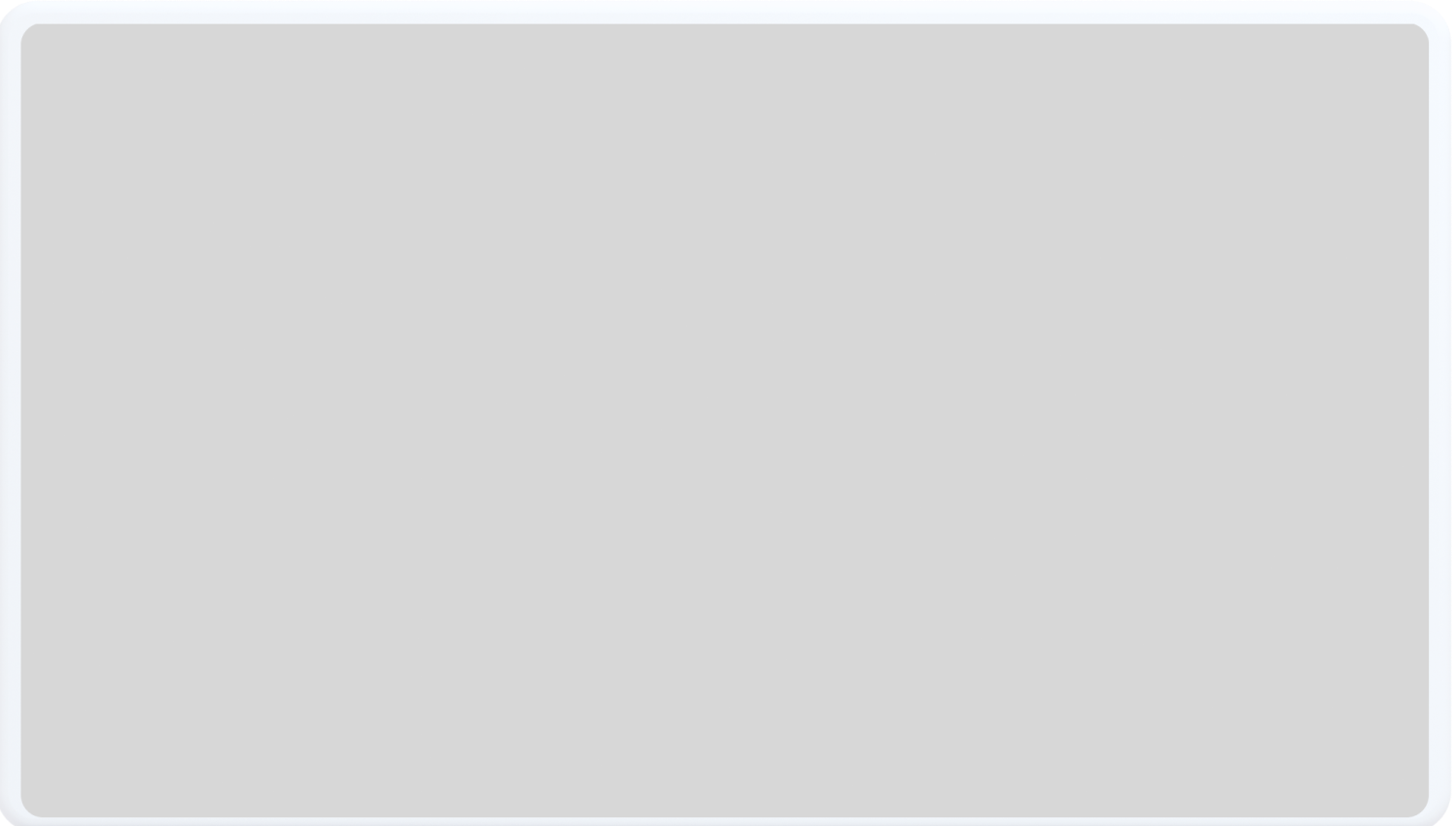

児童相談所の管理者の方のホーム画面
こちらは児童相談所課長がログインした際のトップページです。一定以上の権限保有者は全ての事案一覧や各職員の行動予定をダッシュボードにて確認できます。また担当職員のスキルや案件数を確認することにより、負荷の平準化や事案に最適な担当職員を配置することができます。
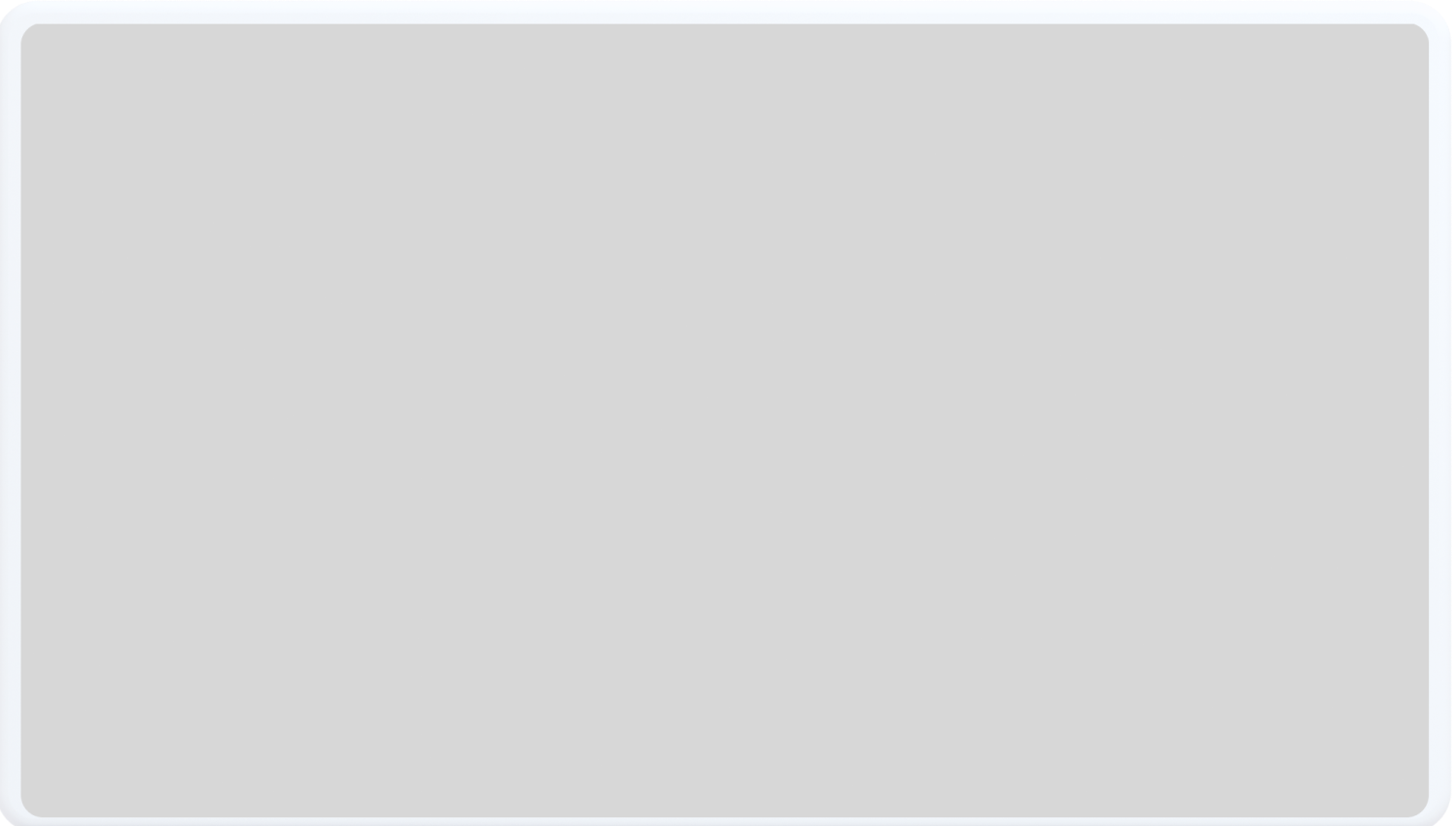

担当者による事案の登録
厚生労働省より提示された「子ども虐待対応の手引き」の「児童記録票(相談・通告受付票)」に基づく通告情報を入力します。リスト化された選択項目により、入力が簡略化できます。既存システムから連携し、通告情報を登録することも可能です。
事案ごとに、重大度・緊急度、進捗状況が一目で把握できます。
また、児童記録票を出力することが可能です。
児童の基本情報や現在の虐待状況、児童を取り巻く関連情報(家族等の関係者情報)等を確認できます。
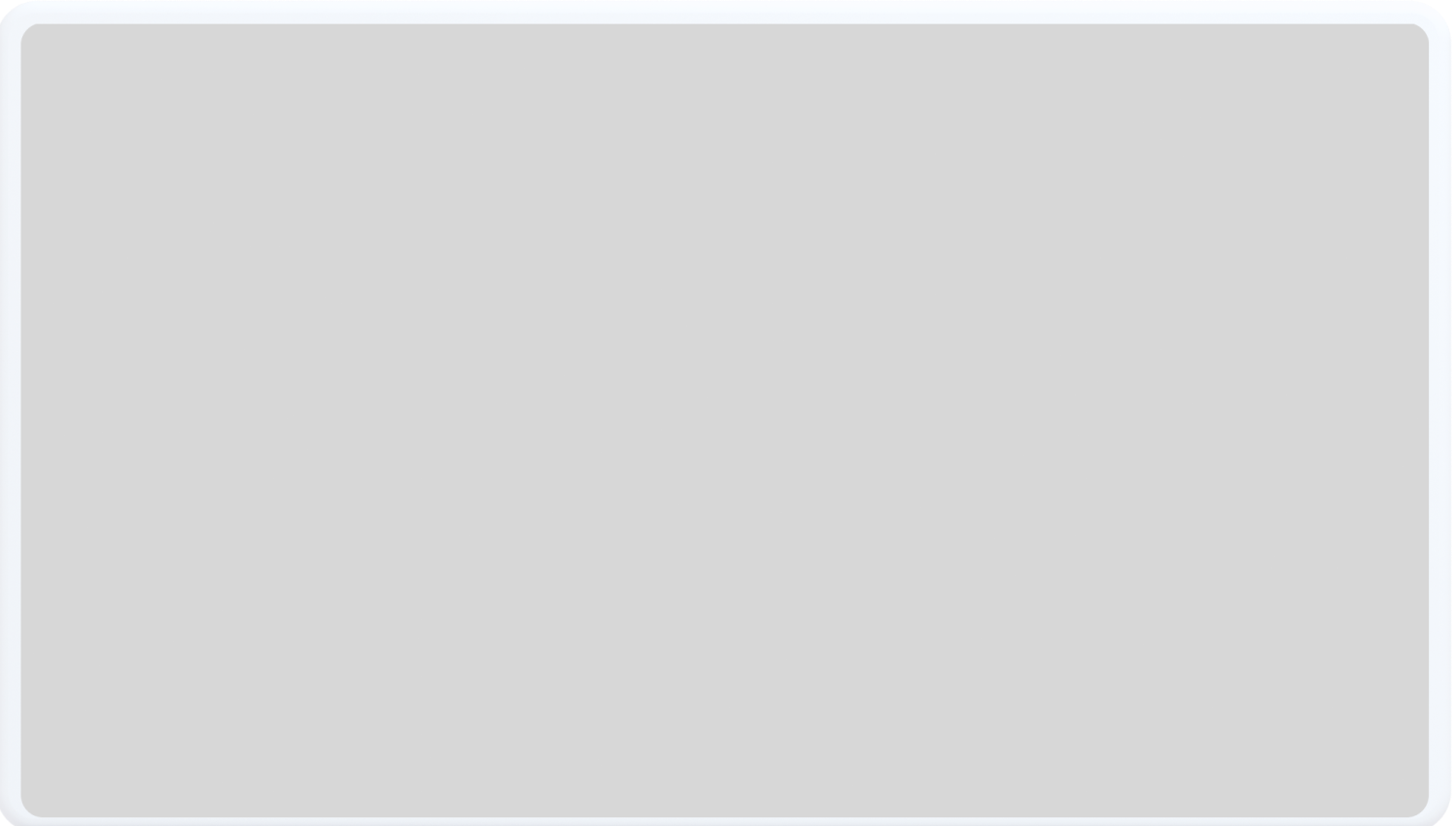

AIを活用した児童のリスクスコア分析
登録された「児童記録票(相談・通告受付票)」の情報 から児童の要支援度合を自動で分析します。担当児童の中から要支援度合の高い児童を即座に把握でき、優先度順に対応することで重大事案の早期発見や職員の負担軽減に役立ちます。児童ごとにリスク要因等の情報を集約し訪問や面談の事前インプットとすることで、より効率的に児童への支援内容を決定することができます。登録データが増えれば増えるほどより精度の高い分析ができます。
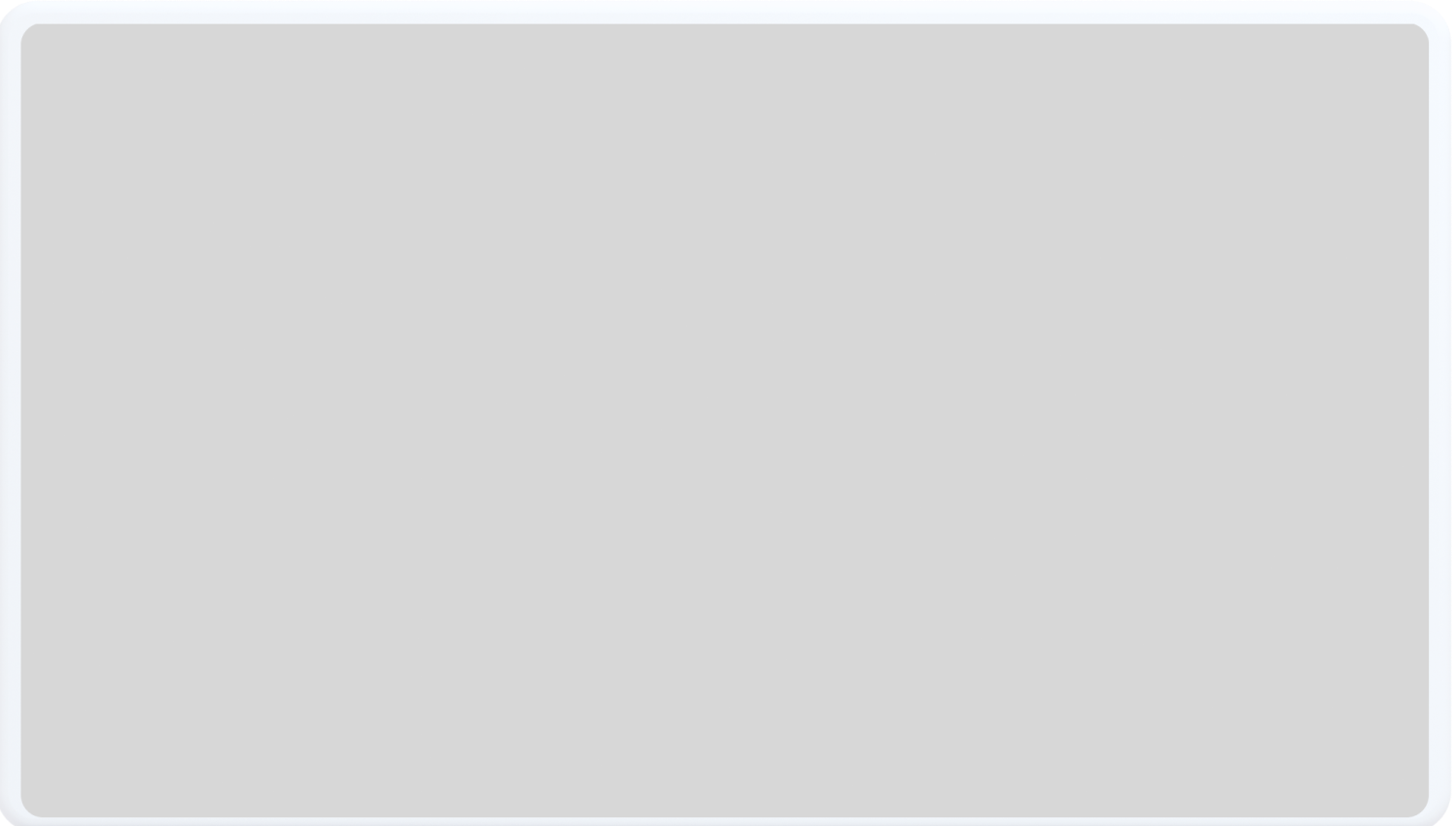
訪問後の結果の登録
パソコン端末だけでなく、タブレットやモバイル端末を利用して、現地や移動時間中に調査結果の入力ができます。
キー操作だけでなく、音声での入力や撮影した写真を画像登録にすることにより入力を簡素化することが可能です。
モバイル端末からのログインは二要素認証を採用しており、セキュリティにも配慮しております。
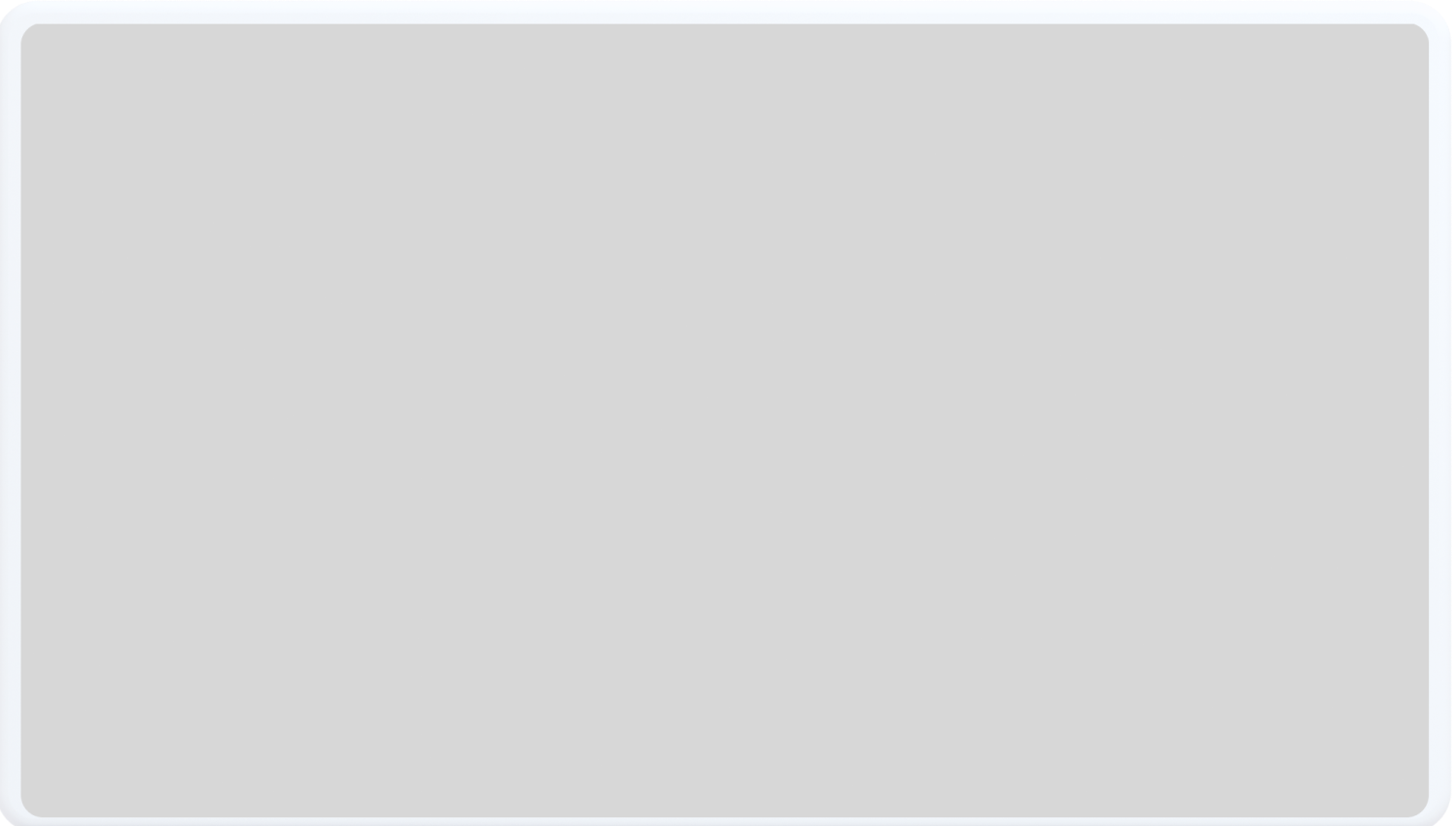

担当者の意思決定支援①
面接結果や児童情報から事案別の意思決定を支援します。これは厚生労働省より提示された「市町村・児童相談所における相談援助活動系統図」の別添5「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」に基づいています。
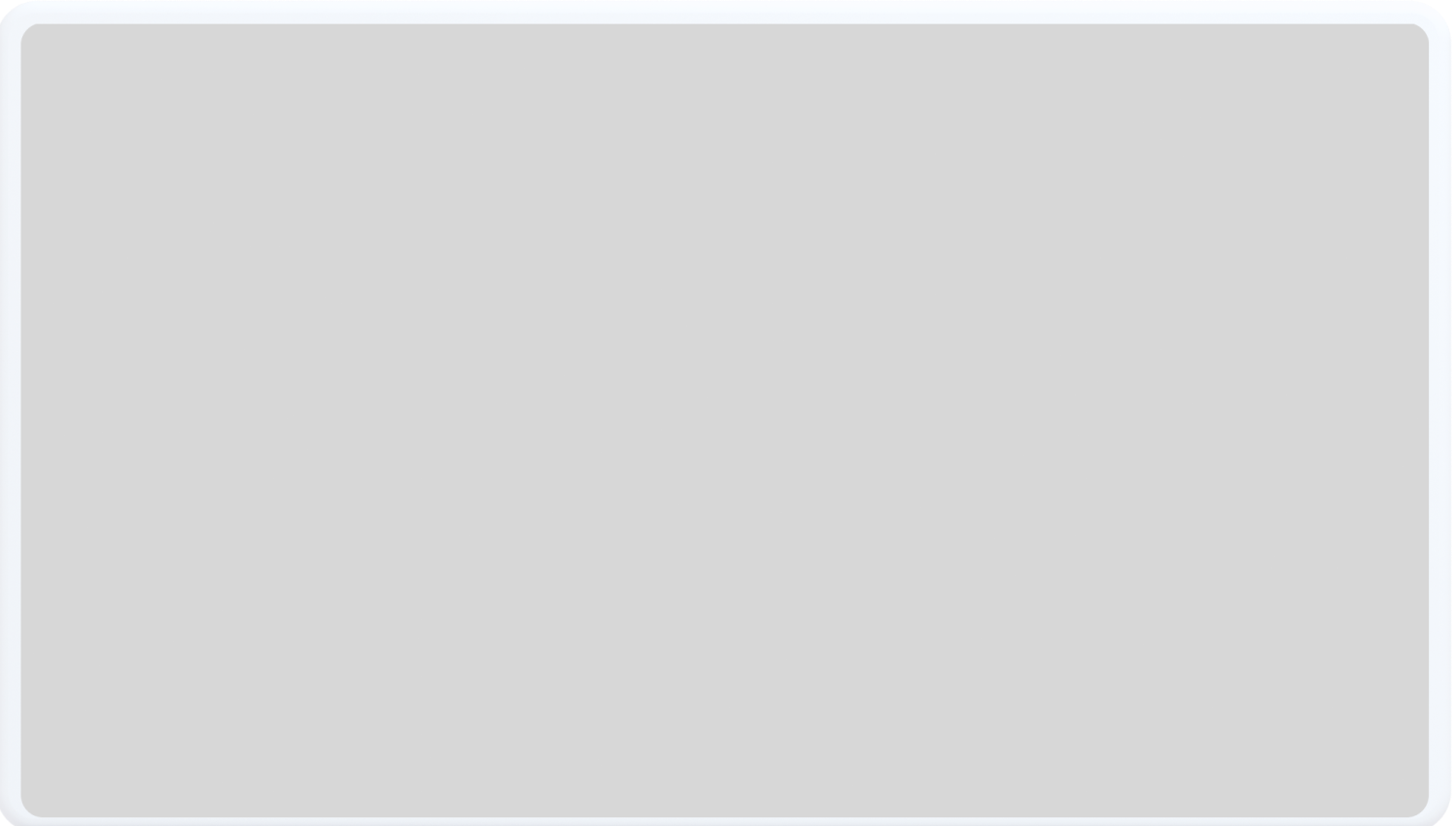

担当者の意思決定支援②
登録された訪問結果を分析し、次に対応すべきアクションを提示することで、意思決定を支援します。職員は、推奨された行動を参考にすることで、より適切な対応を実施することができます。また対応期日が超過している作業や予定がある場合はリマインドを行い、職員の対応を支援します。
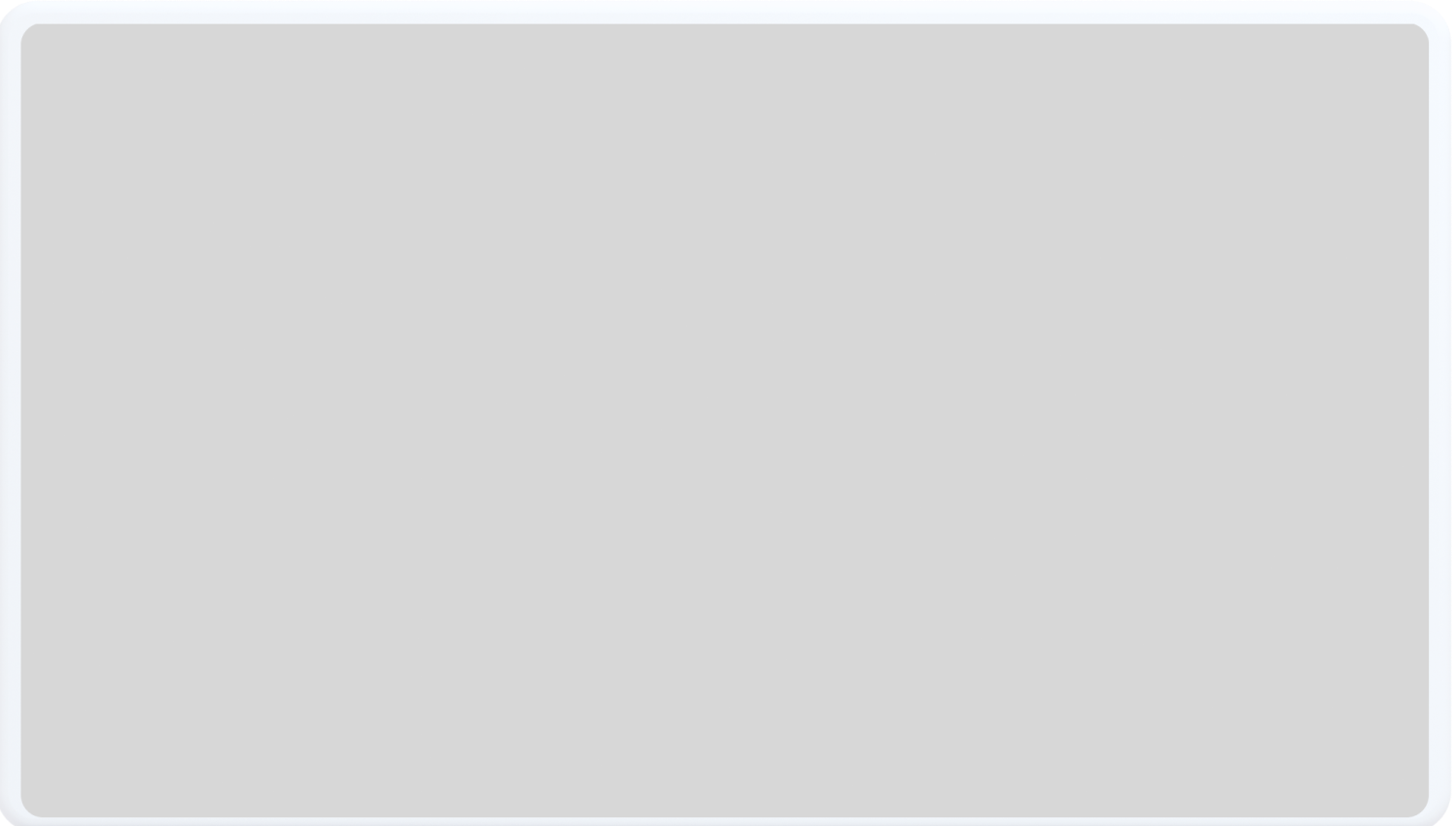
関係者間でのナレッジの共有
同一自治体内の業務マニュアル/ガイドライン/規定に書かれている知識や各担当者の経験の共有を促進します。スキルと経験の属人化を防ぎ、人々の生活を左右する重大な判断を下す責任のある仕事をサポートすることが可能です。単語によるキーワード検索で、過去のノウハウを即時表示します。同意が得られれば、自治体間でのナレッジ共有も行うことが可能です。
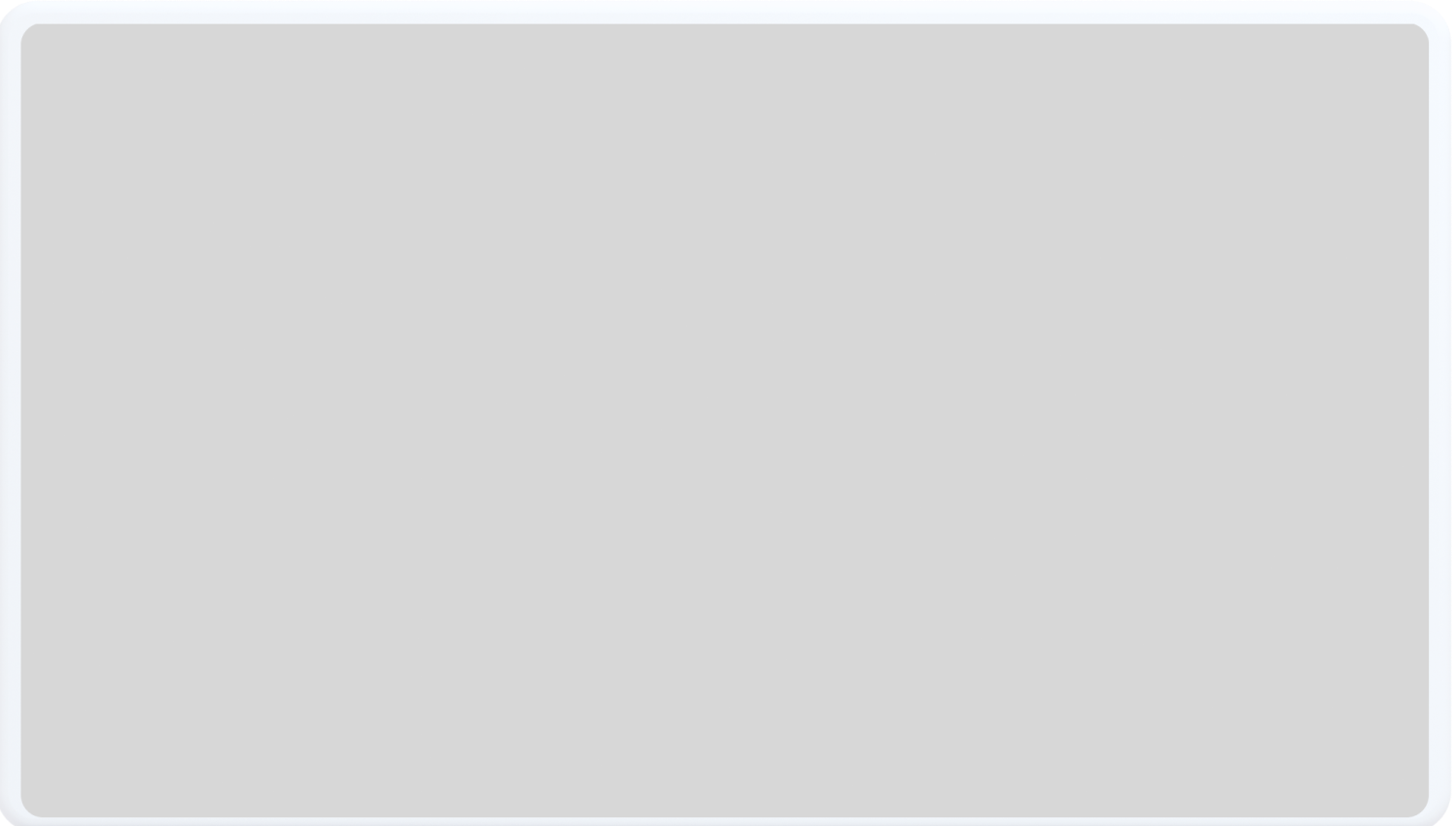

児童相談所における課題
相談ケースの件数増加や慢性的な人材・体制の不足、ペーパーワークの負荷増大、社会的養護体制の不足等児童相談所を取り巻く環境は非常に過酷な状況となっています。
本日は、現場が抱える多様な課題をデジタル技術を活用してどの様に変革できるかをご紹介いたします。
こちらがシステムに最初にログインした際に表示されるトップページです。児童福祉司・児童心理司が抱えている案件の状況をダッシュボードや一覧において確認することができます。また、本日の予定や承認状況も確認できます。
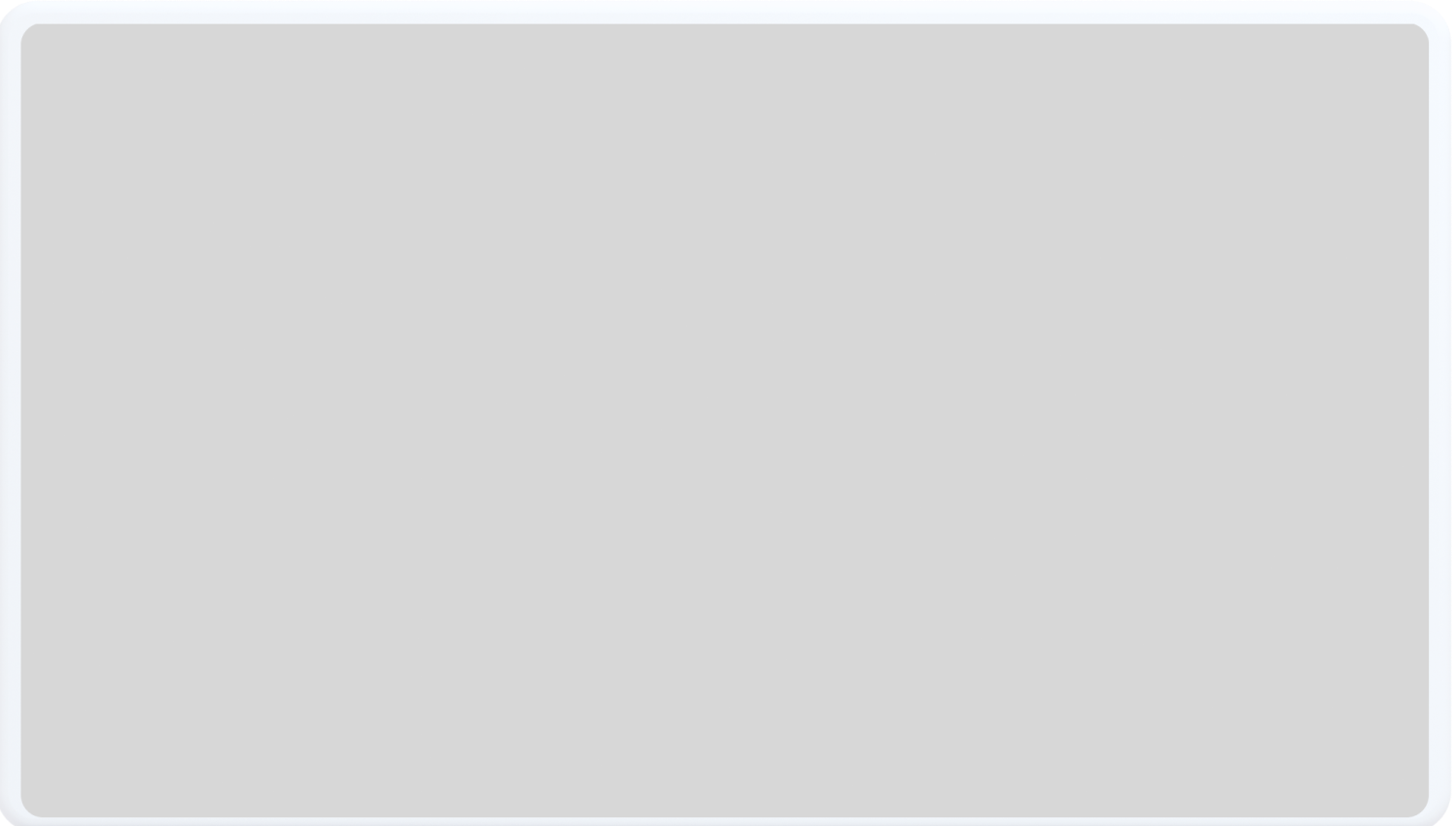

児童相談所の管理者の方のホーム画面
こちらは児童相談所課長がログインした際のトップページです。一定以上の権限保有者は全ての事案一覧や各職員の行動予定をダッシュボードにて確認できます。また担当職員のスキルや案件数を確認することにより、負荷の平準化や事案に最適な担当職員を配置することができます。
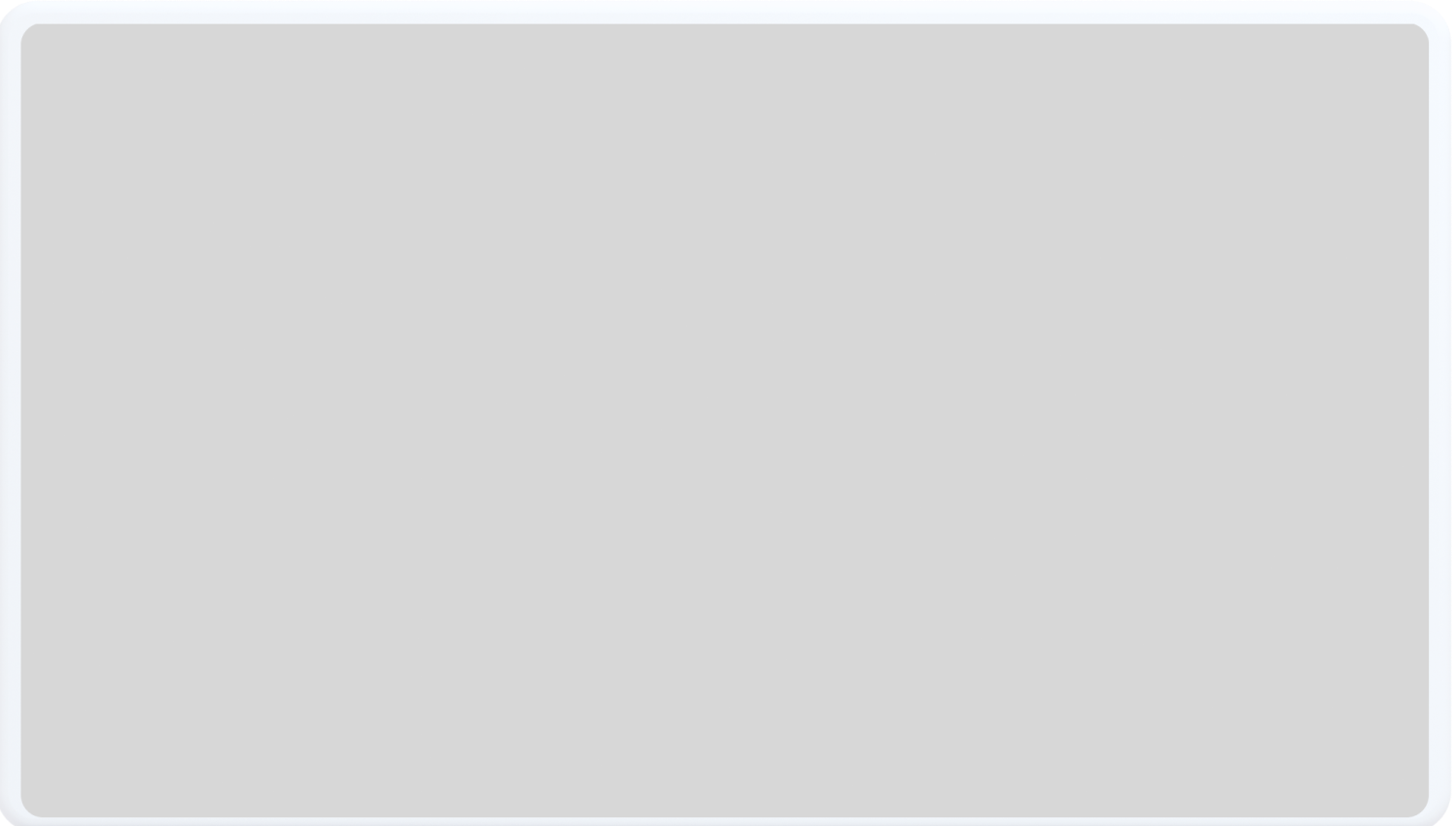

担当者による事案の登録
厚生労働省より提示された「子ども虐待対応の手引き」の「児童記録票(相談・通告受付票)」に基づく通告情報を入力します。リスト化された選択項目により、入力が簡略化できます。既存システムから連携し、通告情報を登録することも可能です。
事案ごとに、重大度・緊急度、進捗状況が一目で把握できます。
また、児童記録票を出力することが可能です。
児童の基本情報や現在の虐待状況、児童を取り巻く関連情報(家族等の関係者情報)等を確認できます。
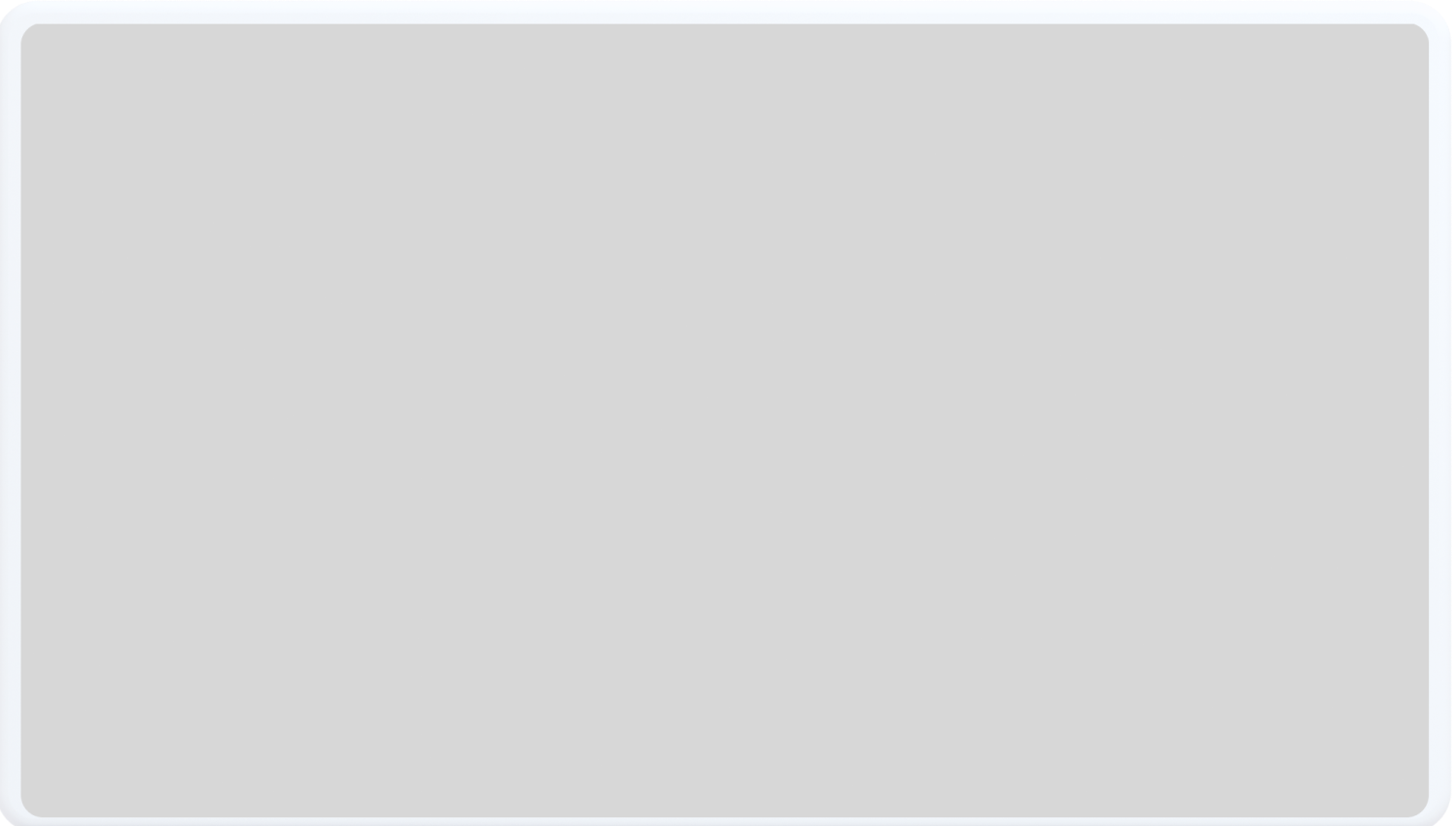

AIを活用した児童のリスクスコア分析
登録された「児童記録票(相談・通告受付票)」の情報 から児童の要支援度合を自動で分析します。担当児童の中から要支援度合の高い児童を即座に把握でき、優先度順に対応することで重大事案の早期発見や職員の負担軽減に役立ちます。児童ごとにリスク要因等の情報を集約し訪問や面談の事前インプットとすることで、より効率的に児童への支援内容を決定することができます。登録データが増えれば増えるほどより精度の高い分析ができます。
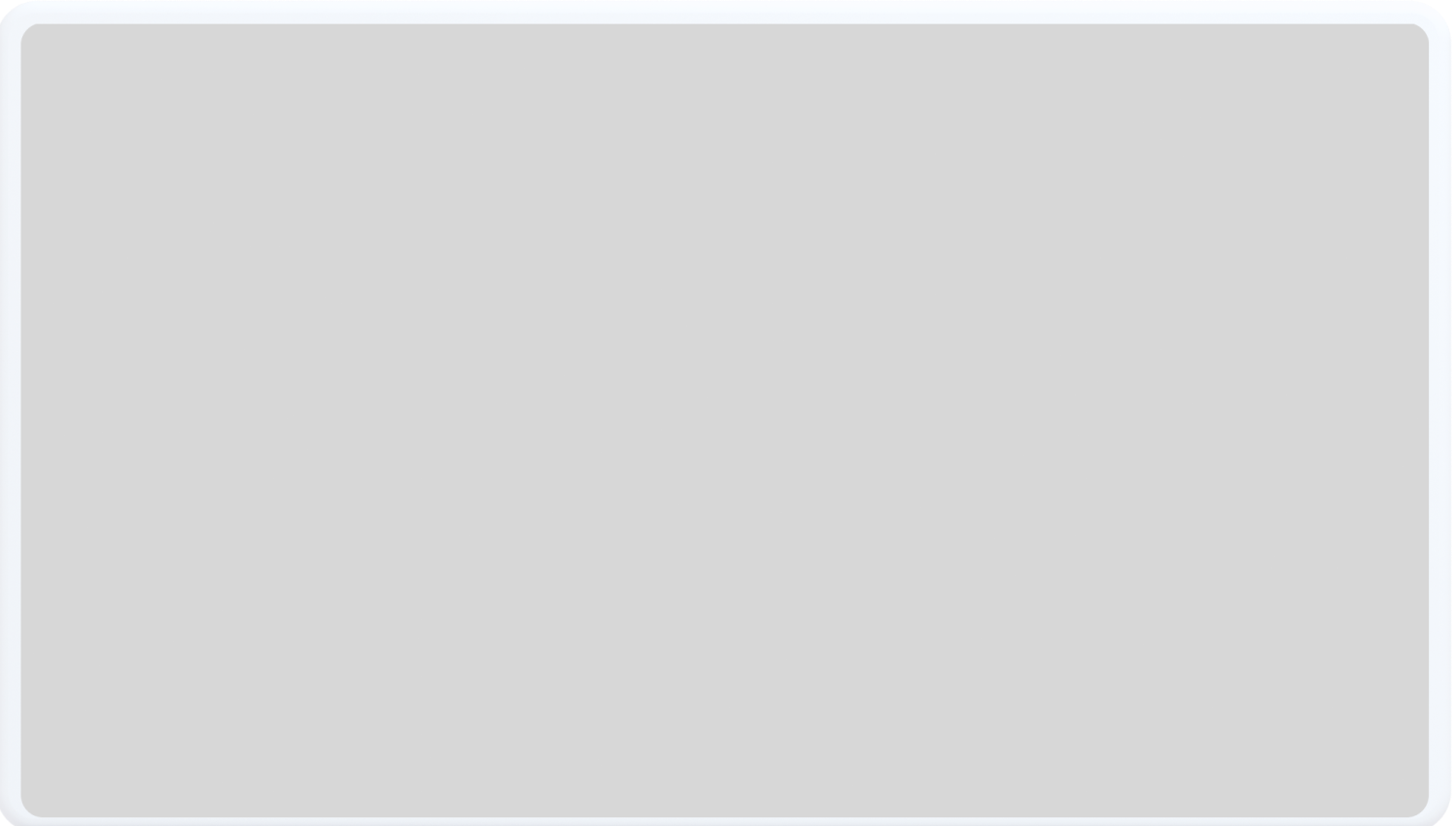
訪問後の結果の登録
パソコン端末だけでなく、タブレットやモバイル端末を利用して、現地や移動時間中に調査結果の入力ができます。
キー操作だけでなく、音声での入力や撮影した写真を画像登録にすることにより入力を簡素化することが可能です。
モバイル端末からのログインは二要素認証を採用しており、セキュリティにも配慮しております。
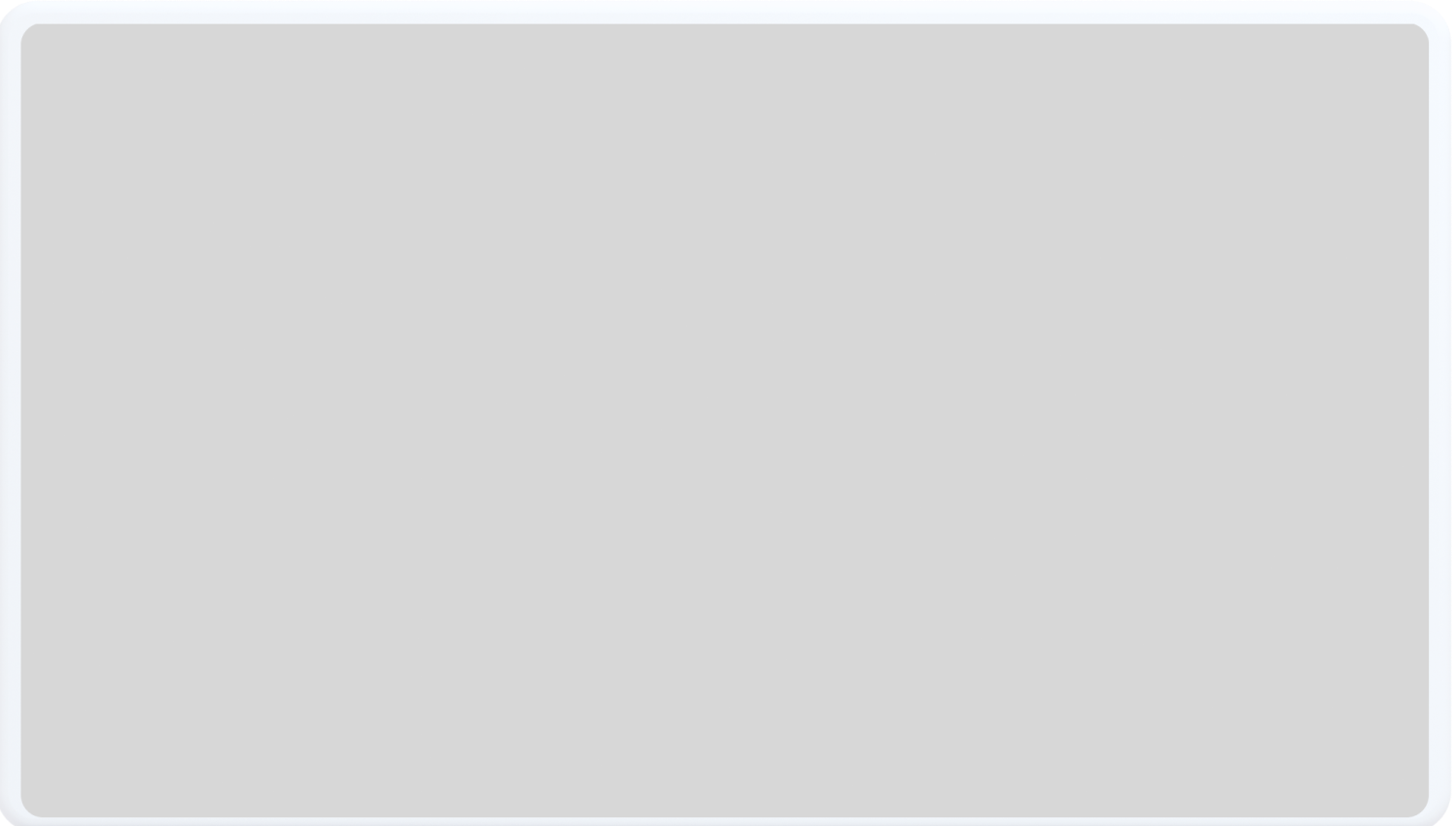

担当者の意思決定支援①
面接結果や児童情報から事案別の意思決定を支援します。これは厚生労働省より提示された「市町村・児童相談所における相談援助活動系統図」の別添5「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」に基づいています。
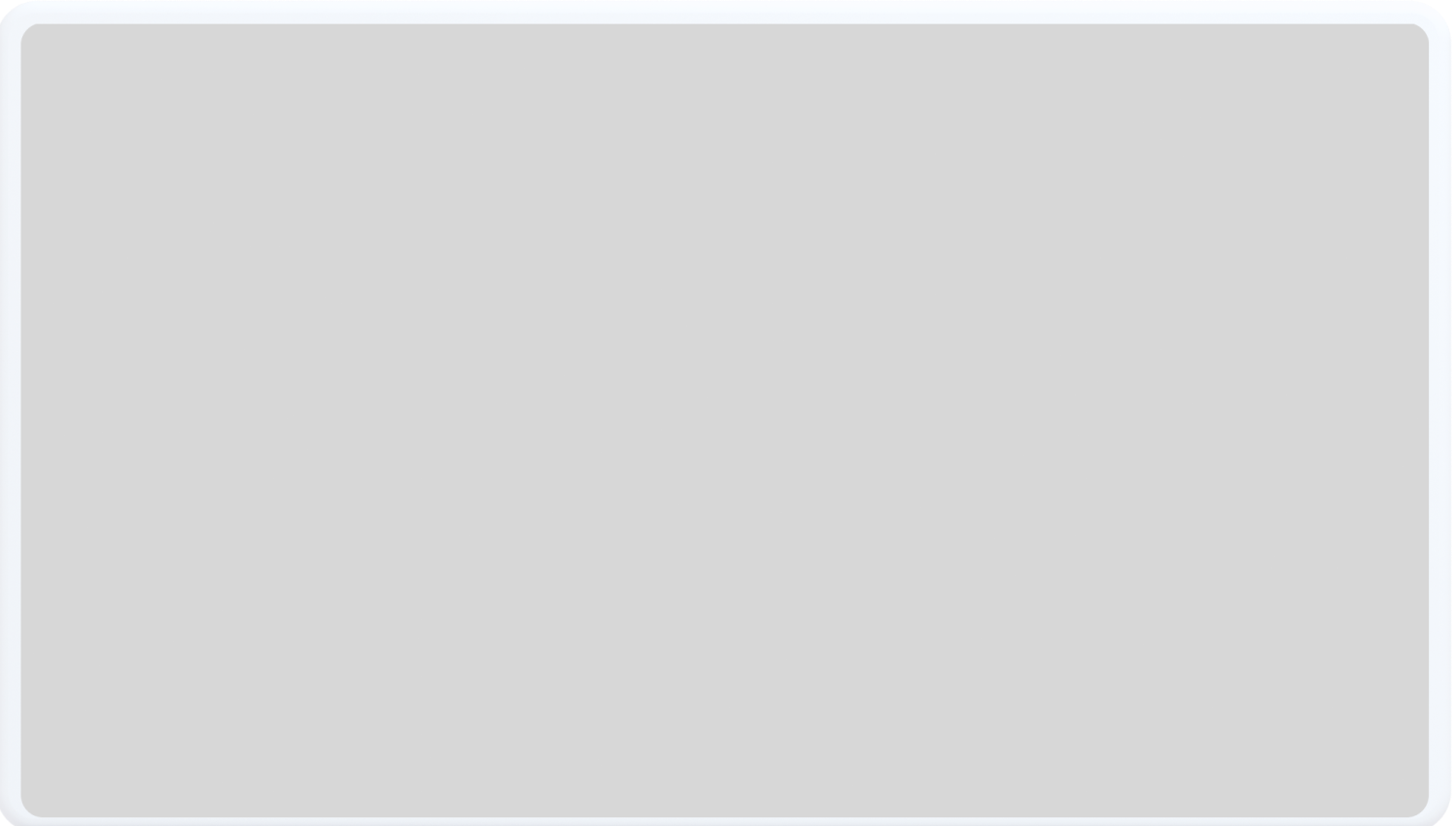

担当者の意思決定支援②
登録された訪問結果を分析し、次に対応すべきアクションを提示することで、意思決定を支援します。職員は、推奨された行動を参考にすることで、より適切な対応を実施することができます。また対応期日が超過している作業や予定がある場合はリマインドを行い、職員の対応を支援します。
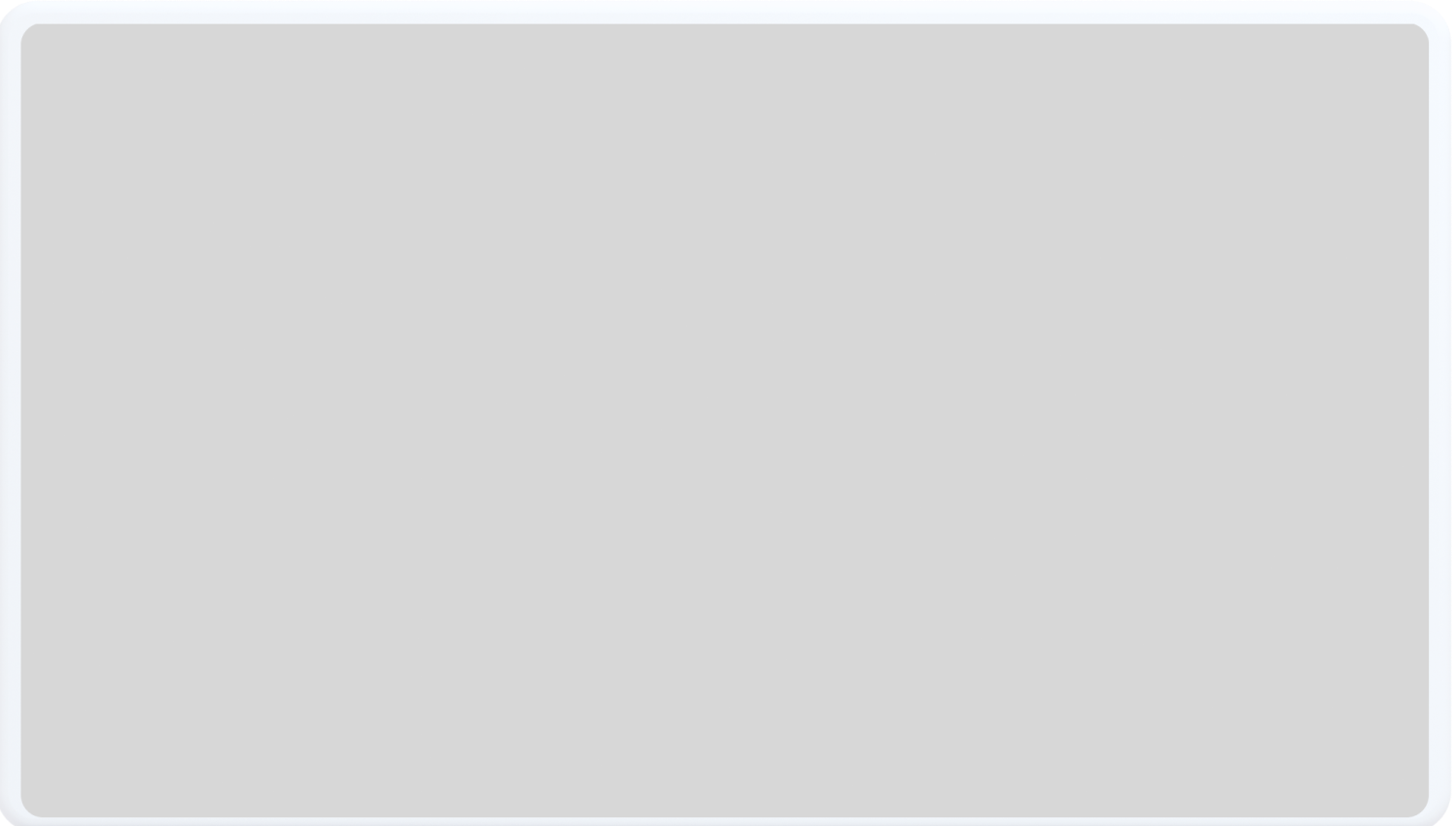
関係者間でのナレッジの共有
同一自治体内の業務マニュアル/ガイドライン/規定に書かれている知識や各担当者の経験の共有を促進します。スキルと経験の属人化を防ぎ、人々の生活を左右する重大な判断を下す責任のある仕事をサポートすることが可能です。単語によるキーワード検索で、過去のノウハウを即時表示します。同意が得られれば、自治体間でのナレッジ共有も行うことが可能です。






